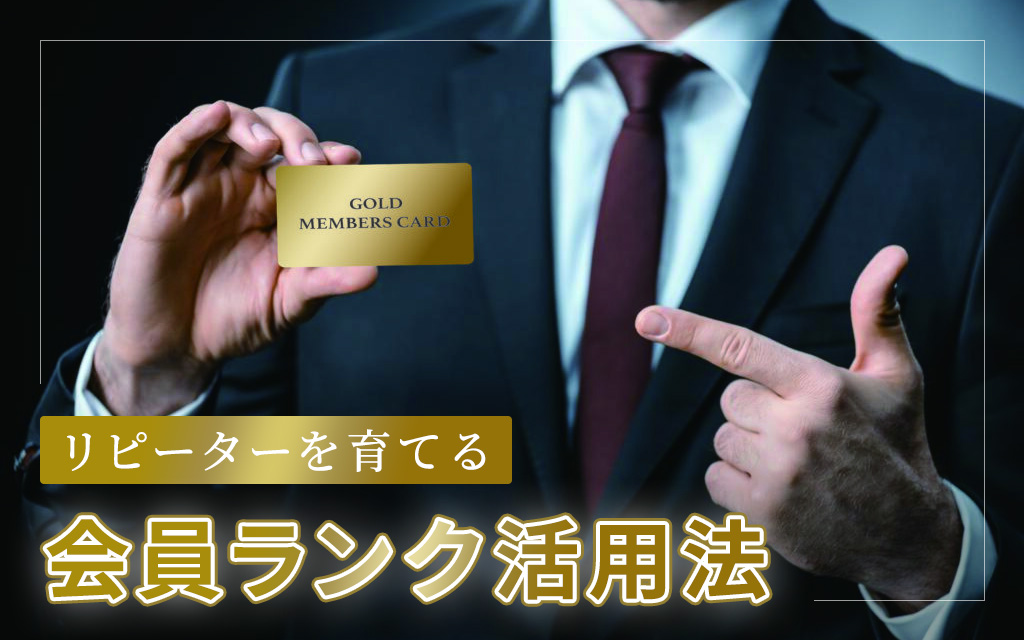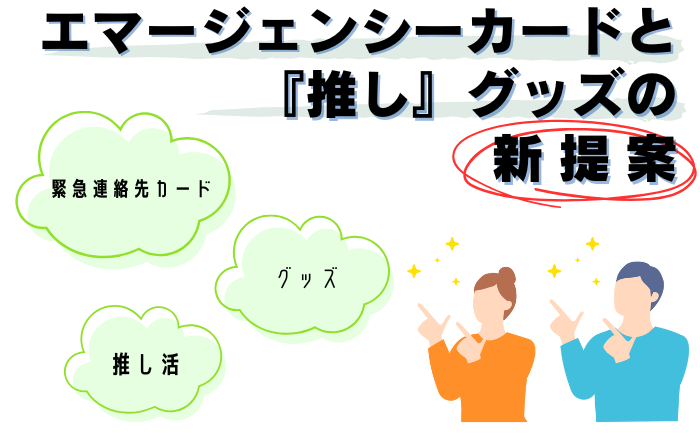クレドカードとは?社員の行動指針となる作成・導入・印刷方法を解説!
- 2025.11.06

近年、企業経営において「クレド」の重要性が急速に高まっています。クレドとは、従業員一人ひとりの行動や判断の基準となる、企業の価値観や行動指針を言語化したものです。
働き方の多様化や社会的な責任が強く求められる現代において、トップダウンの指示だけでは組織は機能しにくくなっています。そこで、従業員が自律的に考え、行動するための羅針盤として、クレドが注目されています。
クレドを従業員に深く浸透させるには、ただ文章として共有するだけでなく、日々の業務で常に意識できる工夫が必要です。その有効な手段の一つが、クレドをカードにした「クレドカード」です。名刺サイズや社員証サイズにすることで、従業員が常に携帯し、いつでも確認できるようにするのが狙いです。
本記事では、クレドが企業にどのようなメリットをもたらすのか、効果的なクレドの作り方、そして持ち運びに便利なプラスチック製のクレドカードを作るメリットや活用アイデアについて、詳しく解説していきます。
企業の「信条」を表すクレド
クレドとは、ラテン語で「信条」「約束」などの意味を持つ言葉。ビジネスにおいては、「会社の方向性」や「従業員の行動指針」、「顧客への約束」など、その会社で働く従業員が心がける「信条」のようなものです。クレドは、トップの意向だけでなく、従業員の話し合いの基で作成されるのが特徴で、従業員の具体的な行動にまで影響を与えるものです。
クレドを導入する必要性
クレドは、従業員が仕事での判断や行動をする際の指針となります。企業活動においては、何かを判断したり行動をしたりする際に、自分個人ではなく会社にとってのメリットや顧客のベネフィットを考えることが必要ですが、クレドはその時の基準となります。
また、社内はもちろん取引先や顧客などに浸透させることで、その会社の価値や目的を広く共有することができます。
クレドと企業理念との違い
企業活動における「信条」というと「企業理念」を浮かべる人も多いことと思います。クレドも企業理念も会社の方向性や会社の意義を述べている点では似ているのですが、クレドと企業理念の大きな違いは作成者です。
企業理念は主に創業時に経営者が会社の存在意義や経営への考え方を定めたもので、内容が変わることはほとんどありません。
一方のクレドは、従業員の話し合いで作成され、周囲の環境や会社の状況に合わせて柔軟に内容を変えていくことができます。
クレド作成で期待できること

クレド作成で期待できることを「社内」「社外」に分けて解説いたします。
1.社内で期待できること
クレドで企業の信条や企業が目指すゴールが明確になることで、従業員が進むべき方向が明確に仲間意識や統一感が生まれます。
従業員の行動や意思決定における明確な基準が示されることで、従業員1人1人が組織の一員であることを意識し、コンプライアンスを意識した行動を取ることが期待されます。
更にクレドで会社の経営方針や判断軸を共有することで、企業の意向に沿った行動を主体的にできる人材の育成や従業員のモチベーションの向上を図ることが期待されます。
2.社外で期待できること
クレドを取引先や顧客に広く浸透させることで、自社への理解を深めてもらうことができます。クレドに自社の進むべき方向や製品やサービスに対する価値を盛り込めば、競合他社との差別化や提供するサービスの向上が期待できます。
クレドを作成する手順
クレドを作成する手順は、
1.プロジェクトチームの選定
2.従業員へのヒアリングやアンケート
3.クレドの作成
4.クレドの文章化
5.クレドの配布
となっています。
1.プロジェクトチームの選定
クレドの作成にあたり、まずは従業員の代表となるチームのメンバーを選定します。多角的な視点から意見を集めるためにも、メンバーは経営陣や組織の上層部だけでなく各部署から様々な役職や年齢の人を選びましょう。
また、クレドの作成にあたっては、プロジェクトの発足時にクレドの目的を具体的に示すことが大切です。「あった方がよさそうだから」「他社も作成しているから」など曖昧な理由でプロジェクトチームを収集しても話し合いがまとまらなかったり作成まで至らなかったりと余計な時間を過ごすことになりかねません。
2.従業員へのヒアリングやアンケート
クレドの目的が明確になったら、従業員へのヒアリングやアンケートを実施します。良いクレドには、実際に現場で働く従業員の意見が反映されており従業員の主体性やモチベーションの向上につながります。できれば全社員を対象にして幅広い意見を集めましょう。
また、社員アンケートに並行して、経営陣へのヒアリングもしておきましょう。クレドは企業理念を前提として考えられるため、経営陣の価値観や判断基準、将来のビジョンなども明確にしておかなければなりません。
3.クレドの作成
社員と経営陣の意見がまとまったら、いよいよクレドの作成です。クレドは、自社で働く全ての従業員の行動指針となるため、社員と経営陣の意見をすり合わせながら作成する必要があります。場合によっては、経営陣と社員が意見交換できるような機会を設けてもいいでしょう。
価値観を共有し、企業からの押し付けではなく、従業員一人一人が「自分たちで考え、決めた」と思えるようなクレドを作成することが大切です。
4.クレドの文章化
クレドの内容が決まったら、まとめて文章化します。企業の信条でもあり、従業員の具体的な行動や判断に反映されるクレドは、簡潔でわかりやすい言葉で示します。また、クレドと実際の行動が大きく乖離しないよう実際に行っていることやできることを具体的に書くようにしましょう。
5.クレドの配布
クレドは作成して終わりではなく、全ての従業員に浸透させ、内容に合った行動を取ってもらうことが最終的な目標です。完成したクレドは、ポスターにして掲示したり名刺サイズくらいのクレドカードにして従業員に配布したりするのがいいでしょう。
ほかにも朝礼やミーティングで読み上げたり、社内メールやSNSで配信したりと常日頃から従業員同士で確認し、評価することが大切です。
有名企業のクレド事例

代表的な企業事例4つをご紹介いたします。
1.ザ・リッツ・カールトン
クレドを最も効果的に使用しているといわれるのが、世界的ホテルチェーンの「ザ・リッツ・カールトン」です。企業理念の『ゴールドスタンダード』に基づいた『サービスの3ステップ』や『従業員への約束』などのクレドにより、リッツの最高級のホスピタリティは提供されています。リッツのクレドは、コンパクトなカードになっていて、社員が携帯して常に確認できるようになっているそうです。
2.ジョンソン・エンド・ジョンソン
『我が信条』としてまとめられた「ジョンソン・エンド・ジョンソン」のクレド。企業が責任を負うべき顧客・社員・社会・株主の4つの存在について示されています。実は、クレドの存在が広く広まるきっかけを作ったのがジョンソン・エンド・ジョンソン。1982年に発生した毒物混入事件の際、企業はクレドに基づいて迅速かつ誠実に対処したと評価されました。
ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、クレド作成から60年以上経った今も、定期的に「クレド・チャレンジ・ミーティング」を実施し、クレドの確認や見直しをしています。
3.ジャパネットグループ
ジャパネットタカタでお馴染みのジャパネットグループは、企業理念の『「今を生きる楽しさ」を!』を基に2007年からクレドを作成しています。ジャパネットグループのクレドは、毎年ブラッシュアップを図っており、その内容は社員証サイズの小冊子にまとめられ、毎年社員に配布されています。
ジャパネットのクレドは、小冊子の表紙デザインまで社員投票で選ばれたもの。細部に渡り「ジャパネットらしさ」を大切にしていることがわかります。
4.小田急電鉄
小田急電鉄のクレドは比較的新しく、2011年12月に作成されました。『みんなが喜ぶロマンスカーにしていこう』という簡潔でわかりやすいクレドは、年々乗客が減少していくロマンスカーに危機感を感じた従業員たちがプロジェクトを作って策定したもの。クレドを作成したことで、従業員の意識や行動に変革が起き、2017年には、1日の平均乗車数が2011年の2割近くまで回復したそうです。
クレドの浸透に役立つクレドカード
クレドの内容をカードにまとめたものがクレドカード。社員証や名刺と一緒に携帯できて、必要な時にさっと取り出して確認できるクレドカードは、クレドを浸透させるのに効果的なツールです。
また、携帯のしやすさを考えると、大きさは社員証ホルダーや名刺入れに入れやすいサイズがおすすめです。紙のクレドカードは3つ折り、蛇腹折りなども可能ですが、あまり分厚いと社員証ホルダーや名刺入れから出し入れしづらくなったり情報量が多すぎてクレドが浸透しづらくなったりするデメリットも考えられます。
プラスチックのクレドカード

プラスチックのクレドカードのメリット・デメリット、当社の制作事例をご紹介いたします。
1.プラスチックのクレドカードのメリット
プラスチックのクレドカードは、紙と違い耐久性があるので、長期間使用してもヘタレることがありません。そのため、多くの企業がプラスチックのクレドカードを採用しています。
2.プラスチックのクレドカードのデメリット
サイズの融通が利く紙製のクレドカードに比べると、プラスチックカードは、紙面が裏表の2面に限られます。とはいえ、限られた紙面に必要な情報を簡潔に折り込めば、わかりやすく可視性の高いクレドカードが作れます。
3.プラスチックのクレドカードの種類
プラスチックカードには、塩ビ製のPVCカードとペット材を使用したPETカードがあります。PVCカードはJIS規格で幅:85.6mm、高さ:54mm、角の丸み:3mm、厚み:0.76mmと決められています。キャッシュカードや健康保険証、交通系ICカードと同じサイズなので、カードケースや財布での管理もしやすいです。
一方のPETカードは、厚み:0.25mmが一般的なサイズ。ショップカードなどに使われることが多く、PVCカードに比べて薄いのが特徴です。
JIS規格のサイズは、機械や決済端末等で読み込むために決められたものですが、クレドカードのように機械での読み込みの必要のないカードであれば、規格外でも問題はありません。実際、会員証やポイントカードではJIS規格より薄い0.48㎜のPVCカードが多く使われていますし、デザインによっては、名刺サイズ(55×91mm)やハガキサイズ(100×148mm)のプラスチックカードも作成が可能です。
まとめ
企業理念やビジョンが、単なるスローガンではなく、従業員一人ひとりの行動にまで落とし込まれることで、組織は大きな力を発揮します。今回ご紹介したクレドは、まさにそのための重要なツールです。従業員の話し合いによって作られたクレドは、企業からの押し付けではなく、自分たちが決めた「信条」として、日々の業務における意思決定や行動の確固たる指針となります。
その効果を最大限に引き出すには、クレドをいかに浸透させるかが鍵となります。その点において、プラスチック製のクレドカードは、名刺入れや社員証ホルダーに常に携帯できるため、クレドを社員の身近な存在にし、意識付けを促す最適な方法です。導入事例が示すように、この実践により、従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めることに成功しています。
もし、貴社が「企業理念を社員に浸透させたい」「社員の行動指針を明確にしたい」とお考えであれば、ぜひ一度、弊社にご相談ください。
用途やご予算に合わせて最適なご提案を行い、貴社のクレド定着を全力でサポートいたします。